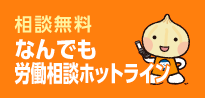- ホーム
- 労働組合のみなさんへ
- 活動
- 福祉・パラスポーツ
- 聴覚障害者のコミュニケーションについて学ぶ ~第4回共生社会実現PTを開催~
聴覚障害者のコミュニケーションについて学ぶ ~第4回共生社会実現PTを開催~
掲載日:2025年2月7日
連合東京共生社会実現PTは2月5日(水)、連合東京3階会議室にて第4回PT会議を開催し、PTメンバーとオブザーバー参加の計24名が参加しました。

第3回PT会議以降の各組織の取り組みについて報告があった後、聴覚障害者のためのオリンピックである「デフリンピック」が2025年に東京で開催されることから聴覚障害者について学ぶために、NHK文化センター手話講座講師である所智子さんからご講演いただきました。
「聴覚障害」と一口にいっても、音声言語を習得する前に失聴してしまった方や、話すことはできるが聞こえづらいため補聴器を使用している方など、様々な方がいらっしゃいます。実際、聴覚障害者の中で手話を習得している方は2割程度で、多くの方は人工内耳や筆談、手話、補聴器などを活用し、コミュニケーションをとられているそうです。
聴覚障害者と会話をする時、「うまく聞こえなかった、もう一度言ってほしい」と言われたら、大きな声で話せば相手も聞こえる、と思われていないでしょうか。聴覚障害者とコミュニケーションをとる際、以下の5つのポイント、耳にやさしい「かきくけこ」が重要であると、所さんに教えていただきました。
「か」…書く(文章全体ではなく、断片的な情報だけでも書く)
「き」…希望を聞く(目の前の聴覚障害者に合ったコミュニケーション方法の希望を聞く)
「く」…口元を見せる(口元の動きを見て会話の内容を読み取るため、マスクを外し、口元を見せる)
「け」…掲示する(指差しコミュニケーションボードを作り、掲示する)
「こ」…言葉を言い換える(「朝食」→「朝ごはん」など、言葉を言い換える)
また、今回の講演では基本的な挨拶「おはよう」、「こんにちは」、「こんばんは」から、デフリンピックにちなんで「デフリンピック」、「陸上」、「水泳」、「卓球」、「柔道」、「サッカー」、「バスケットボール」などの手話も学びました。

連合東京共生社会実現PTは、障がいの有無に関わらず全ての人々が共に生きる社会に向けて、これからも引き続き、様々な取り組みをおこなっていきます。