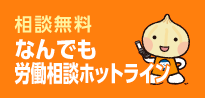- ホーム
- 労働組合のみなさんへ
- 地域活動
- 東京西北地域 西北ブロック地域協議会
- 西北ブロック地協 2025地方自治研修会を開催しました。
西北ブロック地協 2025地方自治研修会を開催しました。
掲載日:2025年9月17日
西北ブロック地協は、9月9日(火)「2025地方自治研修会」を開催しました。
今回のテーマは、頻発する大規模災害を意識して「福祉防災の現状と展望について」と題して、講師に、跡見学園女子大学の鍵屋一教授(観光コミュニケーション学部)をお招きし、46名のブロック地協・地区協の役員、推薦・友好各級議員が参加しました。
まず能登半島地震に触れ、鍵屋教授のご指摘は、死因の多くが高齢者の住宅の下敷きと災害関連死にあり、住宅の耐震化と避難生活支援が充実していれば、状況は変わっていたとのことです。
次に避難所運営の課題として、トイレ不足と栄養不足があったとのことです。このリスクとしては、感染症や誤嚥性肺炎、エコノミークラス症候群にかかりやすく、イライラしてもめごとや犯罪が多くなるそうです。
また降水量について、1980年代と比較して、1時間の降水量が80㎜以上、日降水量300㎜以上の強い雨は、おおむね2倍に頻度が増加しているとのことです。
他にも、75歳以上は30年で3倍に増えていることや、障がい者は12年で43%増加していること、自治体職員は25年で16.5%減少していることによる、脆弱な人々への支援の限界を思い知らされました。
こうした多くの課題がある中、愛知県岡崎市が取り組んでいる「ひなんさんぽ」という良例を紹介いただきました。名前のとおり散歩がてら、近所の知り合いと一緒に集会所に行って、おやつを食べながら、個別避難計画を作成するというもの。この取り組みが、地域の人たちとたくさん話せたとか、新しい友達ができたとか、みんなと一緒だと参加できたといった、地域のつながりづくりに効果が出ているとのことです。
この「ご近所力」を高めることこそ、地域における人間関係やご近所関係を良好にして、災害や危機にも強くなる、めざすべき防災につながる備えになることを学びました。
講演終了後の質疑には、多くの質問や感想が飛び交い、西北ブロック地協と地区協の役員は、これからの政策づくりにとても重要となるヒントとなるものを、たくさん学ぶことができました。