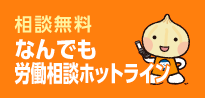- ホーム
- 労働組合のみなさんへ
- 地域活動
- 東京西北地域 西北ブロック地域協議会
- 西北ブロック地協『ボランティア学習会~障害の有無を超えて相互理解を深める~』
西北ブロック地協『ボランティア学習会~障害の有無を超えて相互理解を深める~』
掲載日:2025年11月17日
はじめに、宮本ボランティア委員長から「ご存じの方も多いと思いますが、聴覚障害者のためのオリンピックである『デフリンピック』が2025年11月に東京で開催されます。連合東京、西北ブロック地協も応援していますので、今日は、聴覚障がいについてみんなで学びを深めたいと思います」と挨拶しました。学習会の講師は、NHK文化センター手話講座講師である所智子。実習を交えて、わかりやすいご講話をいただきました。
『聴覚障害』と一口にいっても、音声言語を習得する前に失聴してしまった方や、話すことはできるが聞こえづらいため補聴器を使用している方など、様々な方がいらっしゃいます。実際、聴覚障害者の中で手話を習得している方は2割程度で、多くの方は人工内耳や筆談、手話、補聴器などを活用し、コミュニケーションをとられているそうです。
参加者それぞれ、聴覚障害の認知や理解度が違っていたことを改めて感じました。
聴覚障害者と会話をする時、「うまく聞こえなかった、もう一度言ってほしい」と言われたら、大きな声で話せば相手も聞こえる、と思われていないでしょうか。聴覚障害者とコミュニケーションをとる際、以下の5つのポイント、耳にやさしい「かきくけこ」が重要、と教えていただきました。
「か」…書く(文章全体ではなく、断片的な情報だけでも書く)
「き」…希望を聞く(目の前の聴覚障害者に合ったコミュニケーション方法の希望を聞く)
「く」…口元を見せる(口元の動きを見て会話の内容を読み取るため、マスクを外し、口元を見せる)
「け」…掲示する(指差しコミュニケーションボードを作り、掲示する)
「こ」…言葉を言い換える(「朝食」→「朝ごはん」など、言葉を言い換える)
『東京2025デフリンピック』は11/15開会式、約2週間の熱い闘いが繰り広げられます。連合東京でも、11/16デフバレーボール大会予選を観戦します。デフバレーボールはボールの位置やメンバーの動きを音で判断出来ないので、全て目で見ています。広角レンズのように視野を広く持ってお互いを見ながらプレーしているのは、デフ競技ならではの特徴、と言えます。応援している側は、障害を物ともしないアスリートの活躍に心を踊らされました。
これからも、誰もが個性を活かし力を発揮出来る、共生社会の実現に向けて、運動を進めていきます。